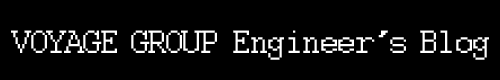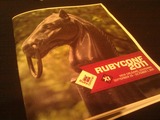こんにちは、システム本部 インフラエンジニアの岩本です。
いきなりですが、弊社には育成制度の一環として、カンファレンスなどへの参加費用を会社が負担してくれる、という制度があります。
そんなわけで私も先日この制度を利用し、アメリカのニューオーリンズで行われたRubyConf2011 に参加してきました。
日本でのRubyカンファレンスであるRubyKaigi(以下,日本Ruby会議) には当日スタッフとして参加していましたが、海外でのRubyカンファレンスは初めての経験です。
今回はその初体験レポートになります。
今年の期間は9/29 - 10/1 の3日間でした。
規模はだいたい400 〜 500 人くらいじゃないかと思います。(大雑把。。)
昨年に引き続き、今年も開催地となったニューオーリンズはJazz の街として有名で、街中ではギターやサックスを奏でる外人さんがたくさんおり、昼間でもライブバーからバンドマンの歌声が聞こえてきているような、陽気な街でした。
特にカンファレンス会場となったホテルのすぐ隣はバーボンストリートと呼ばれる繁華街で、夜になると本当にびっくりするくらいにぎやかで驚きました。

写真: バーボンストリートで演奏する人たち。と、なぜか(?) ピョンピョン飛び跳ねていた上半身裸の男性。陽気ですね。。
■セッションについて

セッションはRuby の仕様に関する話から、Ruby とは直接は関係ないプログラミング環境に関するものまで様々。
Ruby に関するものだけかと思いきや、意外にその他の話題もたくさんありました。
Rubyist 以外のエンジニアが来てもそれなりに楽しめるラインナップだったのではないかと思います。
タイムテーブルはこちらで参照可能です。
また、動画はconfreaks に随時アップロードされているようです。
弊社エンジニアのこしばさんによるLTも視聴できます。まだご覧になってない方はぜひご覧ください。
セッションの内容については、るびま にフィードバックの記事が載る、かもしれません。興味ある方はこちらもチェックしてみてください。
個人的に一番印象に残っているのは、Github の方のセッションでした。(動画がなかったので、スライドへのリンクです。)
ノっているサービス作ってると、セッションもノリノリだなぁと笑。
また今回日本人発表者の中には14歳にしてRubyコミッタとなったsora_h さんも入っており、
英語で堂々と発表するのを間近でみてすごいなぁ思いました。
やはりこういった良いモノを見ると、とても刺激になりますね。
Matz をはじめ、RubyコミッタのみなさまやRuby関連の書籍を執筆されている方など、かなり豪華な顔ぶれ。。
英語能力やRuby能力にかなりの引け目を感じつつも、非常に楽しく交流できました。
ちなみにこういった情報はRubyConf に参加する日本人Rubyist の間でTwitter, MLを使って適宜情報交換されており、現地での行動でも非常に助けられ、あらためてコミュニティのありがたさを感じました:)
また、カンファレンスではホテル内で食事が用意されており、ビュッフェ形式で好きな席に座って食べるため、コミュニケーションを取る機会にもなります。
中には日本語がわかる方も少しいらっしゃるので、まずはそういう方と仲良くなると、他の方にも繋がったりして輪を広げやすいですね。
カンファレンス中には、Tシャツがキッカケでコミュニケーションすることもありました。
(私はTokyoRubyKaigi のTシャツを着ていて、日本好きな人に声をかけられました。
特徴のあるTシャツを着ていくのもキッカケづくりのひとつとして有効みたいですね:)
RubyConfでは食事を朝・昼とだしてくれるので、その関係かもしれません。
日本Ruby会議 ではよく見られるセッション以外の出し物(即席勉強会や、アンカンファレンス、折り紙教室など) は、会場には特にありませんでした。
その代わり、リクルーティング用のブース(というかテーブルがあって人がいてノベルティや募集要項を配っている) がちらほら。
懇親会は、日本Ruby会議 では実行委員主催のオフィシャルなもの(有料) がありますが、RubyConf では少し違っていて、カンファレンス後に毎晩、どこかの企業がスポンサーとなってパーティーが企画されていました。
こちらは参加費無料。
ちなみに日本Ruby会議2011でもHeroku 主催のパーティーが開かれていましたが、アメリカでは企業によるこういったパーティーが一般的なものなのかもしれません 。
確かに、企業からしたら欲しい人材をリクルーティングする絶好のチャンスなのかもしれません。
日本でももっとやったらいいのに、と思います。
# エンジニアからしたら、タダメシ・タダ酒の機会が増えます^_^v
クロージングは特になく、最後のセッションが終わるとあっさりと終了しました。
# もちろん、その後に企業主催のパーティーはありましたが。
全体としては、「ほどよく手を抜く」という部分を感じました。
大事なところは押さえて、その他の部分はまぁまぁいい具合にやる、と。
# クロージングなどはまさにそんないい例かと思います。
確かに全てにおいて何かを継続していくときには、「より良いものを」と思うがあまりハードルが高くなってしまいがちなので、持続可能な仕組みを作っていくうえでは大事な要素かもしれないな、と感じました。
よくよく考えてみると、日本Ruby会議でもスタッフ間では「自分たちも楽しめてこそのRuby会議なので、頑張りすぎず頑張りましょう:)」みたいな空気感があったので、こういった持続可能性に関する空気感みたいなものは共通なのかもしれません。
■まとめ

強引にまとめると、セッションで見たような刺激的な人達・技術であったり、Rubyist コミュニティ の暖かさ、運営に見られる持続可能性などがうまいこと作用しあって、Ruby をこれまで成長させてきた環境ができあがっているのかなぁと。
そんなエコシステムっぽいものを、時には海外ならではの経験から、時には海外から日本を振り返ることで感じられるという、貴重な体験となりました。
長くなりましたが、おそらく私の拙い文章では伝わり切らない魅力がてんこ盛りなので、
みなさんも来年、もし機会があればぜひ参加してみてください:)
※TokyoRubyistMeetup などの機会で、英語に慣れておけるとよいですね! (自戒の念も込めて。)
以上です。
そんなエコシステムっぽいものを、時には海外ならではの経験から、時には海外から日本を振り返ることで感じられるという、貴重な体験となりました。
長くなりましたが、おそらく私の拙い文章では伝わり切らない魅力がてんこ盛りなので、
みなさんも来年、もし機会があればぜひ参加してみてください:)
※TokyoRubyistMeetup などの機会で、英語に慣れておけるとよいですね! (自戒の念も込めて。)
以上です。